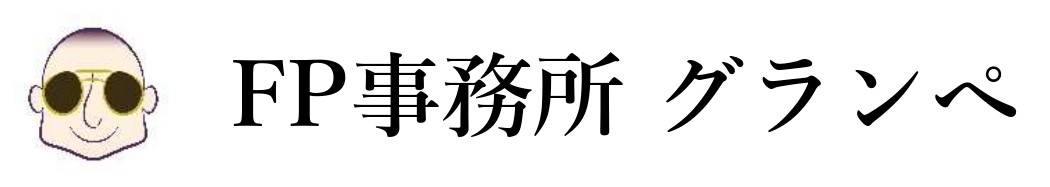このページは、大峠が自分の育ちを振り返り、今の自分の思想や行動原理を自ら整理して認識することを目的として作成したものである。両親から見たらそれは認識違いなのではないか?誤解なのではないか?と思える部分もあるかも知れないが“今の私がこう認識している”ということが重要であり、全ての結果である。むしろ、私の心の中にあるフィクション“大峠物語”だと思っていただいて差し支えない。
Contents
1章 分裂した家庭で与えられた条件付の愛
部屋の明かりを消し、ホールケーキに年齢と同じ本数のロウソクを立てる。"Happy Birthday to You"の歌を歌い終わったらロウソクの火を吹き消して「お誕生日おめでとう!」とお祝いの言葉をかけてもらう。少し気恥ずかしいけれど純粋に自分が主人公で愛されていることを実感する“誕生日祝い”。私はこのような“誕生日祝い”を両親にしてもらったことがない。
私の両親が愛情の薄い人間だったわけではない。基本的に子どもに対する愛情の強い両親だったと思う。それなのに“誕生日祝い”をしなかった理由は、母がある宗教の信者だったからだ(その宗教では誕生日を祝うことは異教の慣習であるとして禁じられている)。どのような宗教か?については次章で必要な範囲で言及するが、この章では、母が信者で父が信者でない“宗教的に分裂した家庭”であったことが私の人格形成に与えたであろう影響に絞って書いていく。
母が信者となったのは少なくとも私が生まれたより後で、恐らく2~3歳の頃である。従って、私が物心ついた時には既に“宗教的に分裂した家庭”であった。原理主義的な宗教であるため、“誕生日祝い”は一例に過ぎず、現代の一般的な生活習慣と相容れない部分があり、家庭生活や社会生活の中で“してはいけないこと”が色々とあった。父はその宗教を子どもに信仰させるようなことは反対であった。母は子どもに信仰させるよう教育することは当然だし父も信仰すべきだと考えていた(その宗教を信仰する者以外は最終的に全員滅ぶという教義である)ため、生活の様々な場面で問題が生じた。
つまり、父はその宗教は信仰しないし子どもに宗教に基づく教育はすべきでないと考えていた(母が一人だけ信仰することは許容したのかは不明)が、母は家族全員が信者となることを目指しており、ことあるごとにその種の“宗教戦争”が発生していた。また、質の悪いことに両親とも少なくとも表面上は“信仰は子ども自身の意志で選択すべき”という立場をとっていたため、何かあるたびに子どもである私は“父と母どちらの側につくのか”という選択を迫られることになった。子どもは親の期待に応えようとするものである。両親の期待が真逆のものであるとき、私は常に辛い思いをした。
父は労働時間の長い会社員であり、母は専業主婦だった。そのため家庭はほぼ母が切り盛りしていて、子どもとしては母側に立たなければ事実上生きていくことは不可能である(少なくとも子どもとしてはそう感じていたはずだ)。そのようなわけで、私は宗教活動に巻き込まれていったし、それが“自分の意志”であると父に表明し、“宗教戦争”の前線に立つ兵士となった。前方には“敵”が、後方には“督戦隊”がいて、どう立ち回ってもどちらかから撃たれるという立場だ。それが“大好きな”両親であったらどれだけ心が引き裂かれるか想像してみて欲しい。
“信仰は子ども自身の意志で選択すべき”という建前が結果的に私を常に父と戦わなければならない立場に置いた。そのようなとき、父は論理的にその宗教を否定しようとしてきたが、私は母から教えられたその宗教の教義に基づいた議論を繰り広げることになった。(現在の)私は世の中の様々な宗教に精通しているわけではないが、ある程度の信者を引き付けられる宗教というのは少なくとも内部では矛盾のない体系的な論理があり、そうそう論破されることのない議論の仕方が定型化されていることが多い。結局のところ議論は最終的に“客観的な証明が不可能な部分についてどちらが証明責任を負うのか”もっといえば“信じたいかどうか”というところに行きついてしまい、決着がつくことはない。このような緊張感のある不毛すぎる議論を両親の板挟みになってしばしば行わざるを得ないことが、私を疲弊させていった。
実際の生活においては、日常発生する葛藤はどちらにもいい顔をしようとすることによって発生した(できるだけ両親のどちらにも愛されたいということ)。母と宗教の書籍を読んでいるときに父が帰宅すれば慌てて書籍を隠して何もなかったかのように振舞った。宗教活動をパスして父と遊びに出かけることもあった。そのどちらの状況でも私は罪悪感に苛まれ、心から楽しむことはできなかった。
この点において、私は家庭の中で“守られるべき子ども”としてではなく、“宗教戦争において味方につけるべき家庭内の成員の一人≒大人”のように扱われていたと思う。当時の私の目線から見れば、“宗教戦争において味方につくこと”が愛されるための条件であった。子どもにとってはまず“無条件に愛されているという実感”が自尊心や自己肯定感を育み、色々なことにチャレンジしていく心のエネルギーの源泉になるのではないだろうか。子どもが子どもらしく子どもとして安心して生きられる場所としての“家庭”というのは非常に重要で、これが損なわれていたことが私の根底部分の自尊心、安心感のような部分に悪影響を与えた可能性は高い。私は成長するにつれて、心の中の吹けば消し飛ぶロウソクの火のような小さな自尊心をその回りに築き上げたコンクリート製のトーチカで守り、まるで明るくしっかりした人間かのように振舞うことで何とか生き抜いてきたが、実際には心配性で自信がなく、悲観的な人間である(ただし、これらの特性は必ずしも人生にとって絶対的なマイナスではなく、仕事や人間関係に生かされている部分もある)。
ここまで読んでくださった方は、宗教のせいでひどい家庭環境となり、さぞ大変だっただろう…と思ったかもしれないが、序盤で書いたように両親は基本的には愛情深かった。家族で楽しい時間を過ごしたこともたくさんあった。家族の良さを体感できた部分も多々あった(にも関わらず、根本では利己主義が優先し、戦いに勝つことが最重要だと学習してしまった)からこそ、余計に辛いのだ。「家族なんてしょうもないものだ」としか思わなければ逆に楽だったかもしれない。
どうしても宗教の話が表に出てきやすいので家庭環境や私の人格形成における全ての問題が宗教に起因するように見えてしまうかもしれないが、そうではない。何らかの原因で深刻な“分裂”が生じていれば、宗教がなくても似たようなことになっていたはずだ。この章では“分裂”がどう影響したか?に絞って書いたが、2章では、“宗教の教義や活動そのものがどう影響したか?”3章では“兄弟の扱いの違い”がどう影響したか?という視点で書いていく。元々は時系列的に書いていこうとしていたが、問題点は概ねその3点に分類できることに気付いたため、このような構成とした。
2章 宗教の影響
「宗教上の理由で、〇〇(学校行事など)には参加できません」と先生に伝えなければならないことが年に何度かあった。そのようなとき、私は何日か前からそろそろ言わなければ…と悩み、勇気を出すことができるよう、神に祈った。
母が信仰していた宗教の教義や宗教活動から直接受けた影響は、功罪ともあると思う。ただ、総じて学校など家庭外での人間関係の構築や様々な関わりを阻害する要素が大きく、子ども時代に学ぶべきことを学び損ねることにつながったことが特に問題だった。その宗教はキリスト教系の新宗教であり、聖書の教えに忠実に生きることを教義としていた(一般的世俗的なキリスト教と比較すると、原理主義的といえる)。その禁止事項は、学校行事などで抵触する部分があり、章冒頭のような場面が学校生活において私の気を重くさせた。
私独自の分類だが、学校活動で抵触しがちな禁止事項には4つの類型があった。第1は、賛美系である。例えば、国歌や校歌を歌うこと、国旗に敬礼することは神以外を賛美することであるとみなされ、禁じられていた。これらは入学式卒業式等の式典、運動会のような行事で発生する。第2は異教系である。異教の神を参拝したり、行事を祝ったりすることは神以外を崇拝することであるため禁止である。具体的は一部の季節行事(端午の節句、節分、ハロウィーン、クリスマス※等)と、研修や校外行事で寺社を参拝することなどが抵触する(訪問すること自体がNGというわけではなく、微妙なところではある)。第3は、戦い系である。これもやや微妙なのだが、戦いが禁じられているため、柔道剣道のような明確な武道は禁じられていた。騎馬戦もNGという解釈が多かった。第4は、時間系である。これは意外と厄介で、可能な限り宗教活動に時間を費やすべきという原則である。学校生活では、授業を受けることや宿題をやることはOKだが、課外活動(部活動)に参加することは基本的に推奨されなかった。課外活動はそもそも学校から強制されないので入らなくても学校との摩擦は起きないが、強制的に帰宅部になることを意味している。
※クリスマスはキリスト教の行事では?と思われただろうが、この教団ではNG。
尚、基本的に聖書の教えに従って生きる宗教なので、聖書で明確に禁じられていることは当然禁止だが、それらは世俗的キリスト教や一般社会、法律の中でも禁止されていることであり、この宗教特有のことではないので触れない(例えば、盗み、殺人も禁止されているが、それは大抵どこの社会でも禁止されている)。ひとつだけ笑い話をすると、信者たちと草野球をしたことがあるのだが「盗塁は盗みなのでなし」と誰かが言って、盗塁禁止のルールで試合が行われた。私はそれを真に受けていたが、実際は冗談で「下手くその草野球で盗塁は刺せないからなしにしよう」というだけのことだった。こんなことを真に受ける程度に原理主義的だったと思って欲しい。
話を学校生活に戻すと、特に学校行事は危険だった。〇〇式と名の付くものがあれば国歌や校歌の斉唱があるかを真っ先に確認し、先生に伝えて安全な立ち回りを確保した。図工の授業であっても「こいのぼりの絵を描きましょう」とか言われるとアウトだし、レクリエーションも「お楽しみ会」ならOKだけど「クリスマス会」ならNGとかどこに地雷が埋まっているかわからない(私が参加できないと言ったことで会の名称を変更することになったこともある、一部の同級生には顰蹙を買っただろう)。それらに参加することは「滅び」を意味し、自らの良心(≒植え付けられた罪悪感)が許さない。幸い、このようなことを理由にイジメにあったりはしなかったが、学校生活において常にいつ教義に反することが求められるかわからず、学校生活を楽しむ部分より恐怖感を感じながら過ごす部分が多かったことは私の積極性や好奇心の発揮を阻害したといえる。
また、今振り返ると大きな問題だったと思うのは、可能な限り宗教活動に時間を費やすべきで、課外活動など必須でない活動には基本的に参加すべきでないという部分である。中学以上になると、何らかの部活動に所属することが一般的で、そこで先輩後輩との付き合いが発生したり、勉強以外の目標を共有する仲間と出会うなど、人間関係を作る能力を発達させる上で重要な過程となる。そういったものを全て放棄することは、学校生活の中で居場所がなくなることにつながっていき、私は中学2、3年の2年間不登校になってしまった。
なぜ不登校になったか?明確な理由はわからないが、感覚としては“精神エネルギーの枯渇”であった。宗教活動そのものとの関連でいえば、学校で教義に反することが発生することへの恐怖(及びそれを先生に伝える億劫さ)と学校活動にフルコミットすることを認めない宗教上の制限が居場所作りを阻害したことが影響したと思われる。学校に行く気力などなくなり、食事をする気力も低下し、蕎麦と巻き寿司しか食べていなかった気がする(余談だが、今でも蕎麦は大好物で、蕎麦すら食べられなくなったら私の命が尽きる時だと思う)。また、前章で述べた“分裂”の問題と次章で述べる“兄弟関係”の問題が家庭内での私の居場所を奪ったことも大きく影響している。つまり、身の置き場がなくなってしまい、行き詰ったのだと思う。不登校とその後については次章以降でも触れる。
さて、ここまで主に宗教上の禁止事項が学校生活に与えた影響について述べた。重複する部分があるが、人間関係の構築に着目して少し掘り下げたいと思う。基本的に、その宗教外での親しい人間関係を作ることは良しとされない風潮があった。外部の人間と仲良くすることは、余計な誘惑や堕落を招くとされていた。特に“行状”の良くない子と付き合わないようにという圧力は一般家庭より強かった。教団外部の人間は基本的に悪であるというイメージが植え付けられていた。こういった事情は「積極的に友達を作ろう」という意欲を減退させ、人間関係において極めて慎重な今の行動にもつながっていると思う。ただ、そうでなくても元々人見知りが強い人もいるし、そこまで関係ない可能性もある。とはいえ、部活動など、学校の授業以外で色々な人と触れ合う機会が制限されたことが私の発達にとって厳しい条件だったのは事実だ。
多少ポジティブな点にも触れておきたい。宗教団体内部では週に3回程度集まりがあり、原則全て参加することが求められ、私も連れられて出席していた。ここにおいては、私は信者の子であり、将来信者になって欲しいと思われていたわけなのでとても歓迎された。新しく集まりに参加するようになった信者候補に対する歓迎の仕方はある程度テンプレ化しており、既存メンバーから積極的に話しかけ、とにかく歓迎や賞賛の嵐を浴びせられる。一般社会からすると少し異様とも思える光景であった。ただ、彼らも子どもの私から見れば、生身のおじさん、おばさんであり、彼らと会話することは私にとって大人との会話スキルを高めるという効果があったかもしれない。少なくとも、宗教という要素を取り払ったとして基本的に皆“とても良い人”ではあったし、可愛がってもらったと思う。また、集まりでは教団の出版物を使った研究が行われ、司会者の質問に対して、挙手して答えるというような双方向のやり取りがあった。この準備のため予習することが求められ、大人が読んでも難しいような文章を小学生のころから読まされていたことが、私の文章読解能力を高めたのは事実である。教義は体系化されており、論理的な文章で書かれているため(今思うと、英語を少し古くて固い日本語に直訳したような文章で余計に難しかった)、国語の成績は常に良かった。
全体としては、宗教の影響で私は学校生活で色々な制限が発生し、教団外での人間関係を作ることが難しい状況に置かれ、家庭内では“分裂”という問題が常にあり、安心して過ごせる居場所がなかったということになる。こういう場合、宗教活動に傾倒してそこを居場所にしていくパターンもあるだろうが、私はやはり心の奥底では信仰がなかったのだろう。精神エネルギーが枯渇し、不登校になり、それどころではなくなった。この期間のことは正直ほとんど覚えていない。脳の栄養不足で記憶されなかったのか、辛すぎて思い出さないようにしているのか、どちらなのだろう。中学不登校期より後のことは4章以降で述べる。尚、小中学生時代の話は次章までで語り終えることになる。次章では、兄弟関係にフォーカスする。重要度深刻度はこの問題が最も高い。
3章 カインコンプレックス
アダムとイヴにはカイン(兄)とアベル(弟)という子がいた。カインは地を耕す者、アベルは羊を飼う者となった。カインは収穫した作物を、アベルは仔羊を神に捧げた。神はアベルの捧げものを受け入れたが、カインの捧げものには目を留めなかった。カインは憤り、アベルを野に連れ出して殺した。
旧約聖書のカインとアベルのエピソードは上記のようなものである。このエピソードを由来として“(主に親の愛を巡る)兄弟間の葛藤、嫉妬や憎しみ”のことをカインコンプレックスという。これは親の愛情や注目が兄弟間で偏っている(と認識した)場合に起こりやすい。“お兄(姉)ちゃんなんだから我慢しなさい”と理不尽に上の子に我慢させたり、“お兄(姉)ちゃんはあんなにできるのにお前は…”と比較して下げるような発言をするべきではない。
私には3歳下の弟が二人いる。仮に弟Aと弟Bとする。AとBは双子である(私は双子ではない、弟が二人いてその二人が双子という意味)。家庭内での私と弟たちの位置付けは違っていた。“お兄ちゃんなんだから我慢しなさい”と言われた記憶はないが、そのようなことは常にあった。第1章でも述べたが、私は家庭内で“準大人”として扱われていたようなところがあった。双子の育児はきっと大変だったのだろう。私は“聞き分けが良くて手がかからない、協力してくれるお兄ちゃん”であることを求められ、親の愛を得たいという子の本能から、自然とその期待に応えるよう行動していた。その結果、ますます私は顧みられなくなり、両親は双子の面倒を見ることに時間や労力を割いていった(その一方、私を巻き込んだ“宗教戦争”も日々繰り広げられていた)。私が“聞き分けが良くて手がかからない、協力してくれるお兄ちゃん”であることで助かったと思っていたかもしれないが、私のフラストレーションは回復不可能なレベルで蓄積していった。
実際にそのようなことがあったかは覚えていない。でも、私の気持ちが少しでも伝わるようにしたいので、次のような場面を想像してみて欲しい。家族5人でファミリーレストランに食事に来ている。両親は双子一人ずつにつきっきりで、 “うどんもあるよ”“エビフライもあるよ”“これは辛いよ”と声をかけながらメニューを選ばせている。私はメニューだけを渡されて一人で選び、“決まった?”とだけ聞かれる。私はとんかつを選んだ。弟たちはエビフライを選んだようだ。とんかつとエビフライが運ばれてくる。“あっ、やっぱり僕もエビフライが良かったな…”と思うが、口には出さない。両親が弟たちにエビフライを食べさせているのを横目に一人でとんかつを食べる。この時の私は“エビフライ”が食べたかったのではなく、“両親と一緒に選んだエビフライ”が食べたかったのだ。家族で過ごしていてもとても寂しかった。
…この文章を書きながら私は泣いている。ここまで散々つらい思い出を書いてきたが、初めて涙が出た。私はただ普通に子どもとして、大事にされていることを実感し、愛されたかっただけだ。愛されたかったがそれを十分実感できなかった日々、取り返しのつかない過去。決して戻ることのない時間。それを今認めるのは惨めな気分だが、せめて自分で自分の本当の想いを認めてあげなければ、自分ですら自分に“いい子”でいることを未だに強い続けることになる。これ以上傷つく必要はない。
さて、ここからはある程度記憶にあるエピソードになる。様々な状況証拠から、中学1年頃の出来事の可能性が高いが正確には覚えていない。家族で車で旅行に行ったときのこと。山道を走っているとき弟Bが“この辺にカナヘビいるかな?探しに行きたい”というようなことを突如言い出した。すると運転する父は車を停めて外に出て、藪に分け入っていった。旅行なので何らかの計画がある。何より私はカナヘビに興味はない。それなのに、弟の気まぐれの要望になぜ付き合わされるのか。これ自体は大したエピソードではないが、積もり積もったものが限界を超えた瞬間だったのだろう。これ以降、私は弟Bの存在を自らの中から抹消した。私はこのとき“カイン”の気持ちが分かった。
父は何かと弟Bに甘かった。兄弟の中で一番甘えん坊の末っ子で、趣味嗜好が一番父と似ていたので、可愛かったのだろう。弟Bの自由でわがままな振る舞いに家族全員が振り回されることは度々あった。母はややその点を懸念していた風でもあった。弟Aも割を食うことが多かったような気がする。弟Bは場の空気を読むことが得意で、自らが有利になるよう巧みに立ち回っていた。私の中では弟Bの存在は生存に対する脅威となっていた。“存在を自らの中から抹消”というのは、弟Bと同じ空間にいることを拒否するという意味である。“家庭内別居”と表現するのがわかりやすい。弟Bの存在を認識するだけで強い憎悪や怒りの感情がわき、正気ではいられなかった。一緒に食事をとることもリビングでくつろぐこともしなくなった。実際のところ、概ね私が自室に引きこもらざるを得なくなった。このタイミングは恐らく中学時代のどこかで、私が不登校になった時期あたりかもしれない。重要なエピソードだが、なぜかいつのことだったのかすら確かなことは思い出せない。
4章以降で述べるが、私は後に弟Aの存在も自らの中から抹消することになる。そして、最終的には家族全員と絶縁状態に至る。文字にすると恐ろしいことのように見えるが、それで私はとても楽になった。脳内を占拠していた余計な苦痛がかなりの程度消えた。だが今でも家族にまつわる悪夢を見て目が覚めることがある。その内容は、概ね、家族と再び関わらなければならない何らかの事態が発生し、恐怖や苦痛を感じている夢だ。昔の嫌な出来事を夢に見ることはない。実際今も苦労しながら思い出して書いているほどに過去のことになっている。
いったいどうしてこうなってしまったのだろうか。様々な要因があるが、結局のところ両親の能力不足だと考えている。私に“いいお兄ちゃん”でいることを期待し、私のフラストレーションに気付かなかったか、気付いていてもケアしきれなかったということだ。双子の子育てはきっと大変だっただろう。だが、厳しいことをいうと、それは上の子である私には関係のないことだ。上の子にとっては、これまで両親のリソースが全て自分に注がれていたところ、下の子が生まれ、リソースが分散してしまう。これは生物として生存に対する脅威であり、下の子が生まれない方が上の子にとっては生存に有利だ(人間の場合色々と複雑だが、単純に野生生物だと考えればそうだろう)。そんな状況で弟ばかりに手がかけられ続け、私は愛されるために余計にいい子になってしまう悪循環。それが最終的に限界を超えてそうなったのだ。
少し動物的すぎる説明をしたが、どうしてこうなったのか、という部分についてもう少しそれらしい考察もしている。“不幸の再生産”説だ。両親がどのように育ったか、私は見ていない。断片的に聞いたことしかないので見当違いかもしれないが、私は次のように推測している。父には妹がいる。父は“お兄ちゃんだから我慢しなさい”的なことを言われて育ったらしい。実際父から語られる昔の妹は妹らしいわがままで甘えん坊な感じの人だ(私に対しては普通に優しい叔母であった)。父自身は私と似たようなフラストレーションを感じていたのではないかと思う。なのになぜ弟Bをひいきしていたのか、それは、弟Bが過去の自分に見えていたからではないだろうか。母の育ちはあまりよくわからないのだが、母の母は子を放置する系のあまりよくない親だったようだ。そのため、母は自分の子に同じような思いをさせないようにしようと思った結果、過干渉に偏り、宗教活動の押し付けのような形でそれが表現されてしまったのではないだろうか。このように、育ちに問題があると、それが自身の子育てにおいて何らかの形で偏った影響を及ぼし、結果的におかしなことになってしまうのではないか。もちろんこれは完全に推測であることを強調しておく。私が納得しやすいようにそう思い込んでいるだけかも知れない。
このような経験から、私は家族を含め、すべての人間関係は利害関係で成り立っており、利害が一致する範囲内でしか協力しないものだという根強い認識が刷り込まれてしまっている。家族でいうと、両親にとっては“全ての子どもがしっかり育つこと”が利であり、子どもたちにとっては“自分が育つこと(両親のリソースをより多く受け取ること)”が利で、競争関係にあると認識している。“父”と“母”も根本的には利害が一致しないと私は考えているが、これは男女対立的な話になっていくのでここでは触れない。
しかし、世の中の家族を見ていると、必ずしもそうではないのだと思う。年をとってもお互いをいたわり合う老夫婦。大人になっても仲の良い親子や兄弟。彼らは家族がとても信頼できるもので、自分の帰る場所があること(帰ってくる人がいること)をとても尊いことだと心から信じている。いつでも玄関に靴を脱ぐ場所が空けてある、それこそがふるさとなのだろう。残念ながら私は持っていないものだが、お金で買えない価値のあるものだと思う。
ここまでの3章では、小中学生時代のことを書いた。私が抱えていた問題3つ(“分裂”“宗教”“兄弟”)について説明することができた。これらの問題により中学2、3年不登校になってしまったが、ここからどのように私の人生が“始まって”いったのかを4章に、5章で私の幸せ(将来)について述べる。ここからは徐々に前向きな話になる。
4章 絶縁状態に至る理由
この章では、中学不登校以降について、概ね時系列で述べる。その後の家族関係、宗教についてはどうなったのか、私はどう決断したか。
これまでの章で述べたように、私は家庭にも学校にも居場所がなくなり、“精神エネルギーの枯渇”により不登校になった。中学2、3年はほぼ登校していない。正直、この間の記憶があまりなく、日々何をして過ごしていたのかわからない。弟Bを抹消し、家庭内別居状態となったことについて、父から“大峠のせいで弟Bまでおかしくなりかけている”と非難されたことだけ覚えている。これはなかなかの放言だ。私がそうなったのは誰のせいかは関係ないのだろう。“大峠がおかしくなるのはまあ仕方ないとして、そのせいで弟Bにも被害が及ぶのは許せない”と解することができる。別に強いショックを受けたりはしなかった。父が弟B側に偏っていたことが原因の一つなのだからその思考のままではさもありなんという発言に過ぎない。
私の記憶が戻るのは高校受験あたりからだ。中学に1年しか行っていないので、出席日数もないし、定期テスト(一応自宅で受けていた)の点数も一桁だったりしたので、まともな高校には進学できない。選択肢は、定時制と通信制しかなかった。定時制の方は定時制とはいえ主に昼間授業が行われており、全日制に近い感覚で通うことができる学校だった。通信制はスクーリングが週1回くらいで、基本的に誰でも受け入れているので本当に行き場がなかった場合の最後の選択肢であり、ひとまず定時制を目指した。セレクションが2期あり、一回目は不合格となったが二回目で合格した。面接や作文?が課された気がするが、どうやって合否判定していたのかは未だに謎である。何はともあれ私は定時制高校に通うことになった。昼間フルタイムで授業を受ければ、3年で卒業することができ、多くの生徒はそうする(単位を落として留年するケースはもちろんある)のだが、私は学力が中1で止まっていたうえ、学校に通う習慣すらなかったためついていく自信がなく、最初から4年かけて卒業することを目指し、余裕のある履修計画を立てた。また、このままでは人生八方ふさがりなのはわかり切っていたため、大学へ進学してみんなに追いつこう、立て直そうと考えた。4年高校に通ってもそのまま大学に進学すれば、実質1浪みたいなものである。
家庭においては、皮肉にも私が不登校になったことにより“分裂”“宗教”の圧力はかなり和らいだ。もはやそれどころではない、と両親も気付いたのだろう。私が高校にちゃんと通えたのは、これらの家庭での問題が小さくなったことにより“精神エネルギーの枯渇”から脱することができたからだと思う。定時制の高校には良くも悪くも多様な生徒がいて、最初の1か月程度で退学してしまう者も多かった。中学不登校や別の高校を退学して入りなおしたような挫折組も結構いて、友達もできた。学校生活を楽しむことができ、よく喋ってよく笑う本来の自分が戻ってきた。このいわばリハビリ期をこの高校で過ごせたことは本当に大きかった。もし通信制高校に行っていたら、そのままドロップアウト気味に社会に出られなかったかもしれない。宗教活動については、高3か高4の頃、母に“信仰がない”旨伝えて辞めた。そういうことを考えて言えるようになったのも私の回復の証だったと思う。特に咎められたり引き止められることはなかった。
学力は高校入学当初の時点では本当に壊滅的だった。国語(現代文)や社会科系は元々の読解力や知識でカバーできたが、英語や数学はからっきしである。ただ、学力レベルの低い生徒も多かったので、授業についていけないようなことにはならず、大学受験を目指して着実に学力向上に取り組んでいった。その結果、高校に4年通った末ではあるが、偏差値60程度の大学の法学部へ進学することができた。このことは自信になり、大学でも成績上位者(上位2%)として給付奨学金を頂いた。また、大学時代は一人暮らしをすることになり、家庭の様々な影響からさらに脱却していった。これ以降は、過去が自分に及ぼした不可逆的な傷を確認し、向き合うという宿題を10年以上かけて行っていくことになる。
詳しくは知らないが、弟Aも中学ぐらいから不登校になっていた。高校にも長年在籍したが恐らく卒業していない。母はそのことを大学に進学した私に相談するようになっていた。私は不登校を“克服”し、高校、大学と進学していて弟Aが今の状態を脱却するにはどうしたらよいか、と考えていたのだろう。私が帰省していたある日、母と弟Aと私でボウリングに行くことになった。弟Aの気分転換のためである。私も久々に家族らしい時間が過ごせると楽しみにしていた。ところが弟Aはボウリング場に到着する直前に気が変わって帰ると言い出した。母は当然のように車を家に向けた。“弟Aは守るべき存在”で、私は“いいお兄ちゃん”。この構図が瞬時に蘇った。私は再び“カイン”となった。私の中で弟Aの存在が抹消された。私はカインコンプレックスを克服などしていない。一生消えることのない傷なのだと明確に認識した。
大学卒業後、私は就職したが、それ以降も両親との交流は続いた。帰省すれば母の手料理を肴に酒を飲んだし、父と趣味の旅行に行ったりもした。両親は今度は私に“親子”として振舞うことを望んでいた。もっといえば、私が去ることを恐れていた。大型連休が近づけばいつ帰ってくるのか?と聞かれ、いついつ自分の家に帰ると言えば、翌日から仕事なのか?もっとゆっくりしていけと言われた。普通は嬉しい言葉だと思う。しかし私はどんどん帰省が苦痛になっていき、帰省中もできるだけ外出し、家に居ないようにした。結局のところ、子どもの頃に受けた傷はなくなったわけではなく“なんで今更親子として仲良くしなければならないのか”“また自分の気持ちを押し殺して彼らの望む振る舞いをしなければならないのか”という自分の本音に気付かざるを得なかった。私にとって“実家”“両親”“家族”とは“満たされなかったトラウマそのもの”であり、関わり続ける限り傷つき続けるということだ。
この過去を清算する方法はあるのだろうか、と考えてみた。私は子どもの頃一番に愛されたかったという気持ちが満たされなかった。これは今どうこうしてもどうにもならない。子どもの頃満たされていたら、私の人格も人生も違ったものになっただろうが、今謝られたり何らかの償いをされても回復するものではない。また、カインコンプレックスについてはさらにわかりやすい。結果として、当時私を犠牲にすることで弟たちを育てることができたという事実がある。この“利益”を失っても私を優先するという行動がなければ、弟の方が優先されたという悲しみは覆せない。究極のところ、私か弟たちか、どちらかの命しか救えないという状況で私を選ぶくらいの犠牲がなければ私はどう謝られても、結局自分が都合よく扱われたと思い続けるだろう。
表現を変えると、私が欲しかった“家族”というものは最初から存在しなかったのだ。両親も弟たちも私にとっては“家族”ではない。こう腹落ちした瞬間、私は両親とも絶縁状態に至る日が近いと確信した。過去の恨みがあるから、今気に入らないことがあるから絶縁するのではない。“もう何も期待しない”から付き合い続ける意味がなくなるのだ。ただ身内ぶって、身内のように振舞うことを望む人たち、それによって過去の問題が解決したように思いたい人たち。私の苦しみをなかったことにしたい人たち。私にとって両親はそう見えた。結論は実は子どものころから決まっていたわけである。
そう決めてから実際に私がそれを両親に告げるまで1年かかった。はっきり意思を伝えること、その後余計なストレスとなるような接触がないことが必要であり、私が求めることを明確にしていく作業が先だった。文字どおり“絶縁”というと、親子や親族の縁を切るという意味である。日本の法律上そのようなことはできない(特別養子縁組を除く)。いくら嫌でも法律上の親族間の扶養義務とか相続の問題から予め逃れることはできないのだ。そのため、一切の接触を断ってしまうと色々と差し障りがある。少なくとも生存確認ぐらいはできるようにしておく必要があった。
2018年末、私は以下のことを宣言した
・今後、居住地や職業等の個人情報を教えないこと
・将来、相続は放棄すること
・私はもう家族ではないこと
事実上、メールか電話でしか連絡が取れないようにした。その後引越をしたり転職をしたりしたが、一切伝えていない。少なくとも私の居住地を知る手段はないはずだ。時折メールが届くが、必要な要件にしか返信しない、必要な内容がなければ返信しないという対応をとっている。毎年私の誕生日に誕生日を祝うメールが届く。“ありがとう”とだけ返すが、それ以上の会話には応じない。今更私の誕生日を祝うのはなぜだろう。少しでも接触したいという今の両親の欲求からの行動であり、本質は何も変わっていない。もはや本当にどうでもいい。
こうして私は過去を全て振り払った。
5章 自分の次元でできることをやる
私は、子どもの頃必要とする愛情を必要な形で十分に受けることができなかったことにより、“無条件で自分は価値ある存在だ”というような根本的な自尊感情や“家族は無条件に信頼できる存在だ”という信頼感が欠如している。愛には常に対価が伴い、条件を満たした場合に受けることができるもので、それは私に価値があるからではない。というストーリーの中を生きている。しかし、世の中それが全てでないことは知っている。ただ、無条件の愛や信頼は相互主義であり、私がそれを与えることができない(というより、私の中に存在しない概念である)以上、それを望むことはできない。子ども時代に起こったことに起因する人格形成については(それが人生の序盤であればあるほど)、後から変えることは困難だと考えている。
私にはこれらの自分に与えられた条件は変えられないため、“自分の次元でできることをやる”という方針で生きている。今考えたらもっとこうできたのでは?ああしていたら?と思うことは大学時代以降も色々とあるが、基本的にそうせざるを得なかったのだと思う。せっかくいい大学に入った(同期には弁護士をはじめとする士業に就いた人や大企業で活躍している人が多数いるはず)のに、サークル活動等もゼミ活動も行わず、ほとんど人脈を作れなかった。中学以降の積み重ねが不十分で、そういう多様なコミュニケーションに耐えられるレベルまで育ち切っていなかったから、いきなりそこまではハードルが高かった。社会人になってからは、もっと上司や先輩を信じて、懐に入っていってチャレンジすればより有意義な経験ができ、成長のチャンスも広がったと思う。人を信頼することが難しい私にとっては、会社で出会う人も私を搾取するかもしれない人といういわば“仮想敵”という見方からスタートするため、それが成長を妨げたり摩擦を起こす要因になった部分はあった。家庭から離れた後も、私は少しずつ自分の足りない部分を成長させ続ける必要があり、これが過去を克服することでもあるのだろう。
ただ、一つ気付いたことがある。大真面目にいっているのだが、酒に酔うことで自分の中でガチガチに凝り固まった、自分を守るための様々なブロックが相当程度解除される。酒を飲みながらなら初めて会う人にも心を開きやすいし、何より新しいアイデアが浮かんでくる。飲まなければ新しいことは何も思いつかない。ここだけの話、大事なことは大抵飲みながら決断したし、いいアイデアは常に飲みながら思いつく。毎日飲んでいたら身体が潰れるので、実際には週2回くらいしか飲酒しない。一人で飲んでいるときは思いついたアイデアをメモしておくようにしている。シラフの状態でそうなれれば最強なのだが…私にはまだ解放されていないポテンシャルがあるような気がする。
ともあれ、毎日泣きながら暗い水底の中で暮らしているわけではない。私は私で前向きに楽しく生きている。誰かと話をすること、つまみを自作して酒を飲むこと、カエルの合唱を子守唄に眠ること、これらは尊いことで幸せな気分になれることだ。このような日々の小さな幸せを感じながら寿命が尽きるまで過ごせれば私は満足だ。家族を作って子どもを育て、子や孫に囲まれて天寿を全うすることを目指している人たちからしたら、私の目指す幸せは“何と次元の低いことか”と思うかもしれない。しかし、私とあなたは違う。あなたはあなたの幸せを追求して欲しいし、可能であればそのお手伝いをさせて欲しいとも思うが、自分が幸せであることを確認するために、私の幸せをくだらないことだと言わないで欲しい。心からそう思っているなら、それはあなたの想像力がなさすぎる。
そう思うからこそ、私は誰のどんな夢だって尊重する。例えば、仕事をやめて低支出のギリギリの生活でも、ただ穏やかに暮らしたい。そんな願いはしばしば蔑まれるが、それが本当にその人の幸せなら、それを本気で追求すればいい。“自分の人生を自分で決める”ことは人生の本質だ。ただ、自分が本当に望むことは何か、その本質は何か、それはどうすれば叶うのか(仕事を辞めたいのはなぜか、自分の幸せ=仕事を辞めることなのか)ということはまず真剣に考えた方がよい。それは他のどんな夢でも同じだ。逆のパターンで、お金を増やすことが幸せだと思い込み、家族も自分も顧みずに働いてお金を追求し続けた結果、多額の資産を作ったが自分が求めていたことはこれではない、とそこで初めて気が付くというのもよくある話だ。
お金をうまく扱うことは、家族の幸せを守ることにつながる。“信じられる家族”という存在を確信できない私には自分で家族を持ち、強い信頼関係を築く自信はない。私は歪に育ってしまっており、不幸の再生産になるかも知れない。そんな私の元に生まれてくる子どもはかわいそうだと思ってしまう。でも、お金の計算や教育なら私にもできるはずだ。他の家族の幸せを守ることをサポートすることによって、間接的に家族の幸せを守ることに貢献できるのではないか。そのことで私も少しでも“家族”という概念がもたらす幸せを感じられるのではないか。自分の人生から逃げるような奴にそんなことをいう資格はない。と思われても仕方がないかもしれない。だが決していじけているわけでも自己憐憫にふけっているわけでもない。欲しいものが全て手に入る完璧な人生などない。不本意なことがあっても“出来ることをやっていく”自分に与えられた条件で“出来ることを叶えていく”ことこそ前向きな人生だと信じている。
幸いなことに、私はこれまでの人生で、また今現在も私のことを単純な利害ではなく信頼してくれる人や、利他的に手を差し伸べてくれる人に何人も出会ってきた。そのような人たちのおかげで私は人間のままでいることができ、本当に心から感謝している。両親にも感謝“すべき”ことはたくさんあると思うが、そこまで自分の心を客観的にコントロールすることはできない。
そのようなわけで、私は“自分の次元でできることをやる”という方針で生きており、FPとしては“自分の人生を自分で決める”“家族の幸せを守る&より大きくすること”に貢献したいと思っている。
サイドストーリー
私は不自然なほど過去の記憶がないのだが、どうもそれは思い出すと心が壊れる恐れがあるので、思い出さないよう脳が自主規制しているということらしい。実は記憶自体はたくさん残っているようだ。思い出したくないような過去は私が自分という人間が何者なのかを認識する上で非常に重要なパーツである可能性が高く、精神的負荷は高いが、可能な限り思い出して再評価していきたい。記憶の断片をサイドストーリーとして書き記していく。
クジラ事件とクジラ汁事件
当時その宗教には「クジラ」を食べてはならないという不文律があった。輸血を拒否することで有名な宗教だが、その根拠は聖書中の「血を食べてはならない」とする記述である。従って、輸血だけではなく適切に血抜きされていない肉も食べてはならないと解されていた。一般に食肉は血抜きされているので問題ないのだが、鯨肉は「適切な血抜き」がされていないと認識されていて(なぜそう認識されていたのかは不明)、事実上禁忌扱いとなっていた。「血の罪」というのは極めて重い罪であり、これを破ることは永遠に滅ぼされることを意味する、当時の私としてはそのくらいの認識だった。そんな宗教の信者だった母と信者でない父との板挟みになった2つのエピソードを思い出したのでここに記す。
クジラ事件
家族で旅行に行ったときのこと、恐らくは宿泊施設の食事会場で起こった出来事だと思う。私の左に母が並ぶ形で座っており、正面に父が座っていたのは覚えている。その感じだと弟たちは父の横だろうか(この席次は珍しい)。
テーブルの上に食事が並んでいるが、その中に正体不明な小鉢があった。母はテーブルの下で自分の左の手のひらに右の人差し指でゆっくり文字を書いて私に見せた。「く」「じ」「ら」の3文字である。父に気付かれないように、私にその小鉢はクジラだから食べないように、と伝えたわけである。この指示には2つの要素があり「父に気付かれて空気を悪くしないこと」「クジラは決して食べないこと」これらを両立することが要求されていた。随分とムシのいい指示ではないだろうか。私は1回で「く」「じ」「ら」の文字とその指示の意味を悟ったが、わからないふりをしたため何度か母が指文字をやり直したのは覚えている(一回で悟れば父にはバレなかっただろう、しかしそれは私が母の無理のある指示を遂行する義務を負うことを意味する。それならはっきり言えばいいのに、とイライラし、わからないふりをした記憶がある)。
そして、この後何が起こったのかは覚えていない。父にも悟られて「何か良くないこと」が起こったような気がするのだが、思い出せない。ちなみにこれは私が小学生の頃の出来事なのは確実だが、何年生頃のことか(私は低学年と高学年で全く別の地方に住んでいたため、どちらかによって行く旅行先も違うはずだが、どちらなのかも思い出せないのは不自然な感じがする)覚えていないし、どこに旅行に行ったときのことかも覚えていない。季節も覚えていないし、旅行中にどこで遊んだかとか、他にどんな出来事があったかも何も覚えていない。記憶が蘇ったのは「く」「じ」「ら」の件だけである。
クジラ汁事件
これは家で起こった出来事で、私が小学校4年~6年の間の出来事だとわかっている。当時住んでいたマンションの景色が思い出せているからだ。
ある日曜の朝のこと、父が鍋いっぱいに「クジラ汁」を作った。父の出身地の郷土料理だという。父は「口に合うかわからないけど、パパの子どもの頃の思い出の味なんだ。一口食べて美味しくなかったら残していいからね」と笑顔でお椀にクジラ汁をよそってくれた。「クジラ」である。家族の中には緊張した空気が流れた。私も弟たちもクジラ汁には手を付けなかった。父は鍋いっぱいのクジラ汁を、怒りと悲しみを込めて(かつ当て付けがましく)流しに捨てた。どんな言葉のやり取りがあったかは思い出せないのだが、その姿だけははっきりと脳裏に浮かんでくる。
家族の不一致、父を喜ばせる行動と母を喜ばせる行動が矛盾するという状況は子どもの心を破壊する。私が宗教的に分裂した家庭で苦しんだというのはこういうことである。この「クジラ汁事件」と「クジラ事件」はどちらが先に起こったことなのだろう。父がどの程度「クジラ」の禁忌を認識していたのかによって「クジラ汁事件」の解釈は変わってくる。「クジラ」の禁忌を十分認識した上での行動だったとしたら、これは家庭内宗教戦争の色合いが強く、父の行動はある種の示威行為というか、クジラ汁を捨てるところまで計算した上でやっていた可能性がある。そうであれば余計な苦痛を与える行動だったと言わざるを得ない。もちろん宗教問題については、おかしな宗教を信じてしまった上に子どもにもそれを強要し、家庭内宗教戦争を引き起こした母がそもそもの原因である。父は常にその宗教を受け入れるよう不当な圧力を受け、家庭内の平和はそれにかかっている状況となり(いわば家族の幸せ自体が宗教に“人質”として取られている)、何らかそれに抵抗する必要があり、子どもの奪い合いから手を引くことはできなかったのだろう。
父も母も「子どものことを第一に考えている」つもりでありながら実際の行動はそうではなく、自分の都合で子どもを振り回し、心を傷つけていたと当時認識できる余地はなかったのだろうか。今更考えても仕方のないことだが、その思いは今でもふとした瞬間に湧き上がってきてしまう。